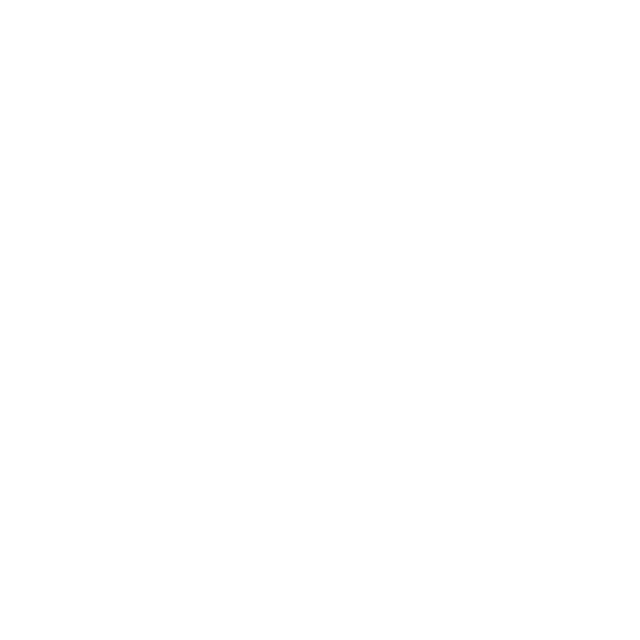9月も気がつけば半ばに差し掛かる週末、中秋の名月ということで、せっかくなのでお月見団子を作ってみました。
芋名月とお団子の形
中秋の名月に月を愛でる慣習は中国から伝来したものですが、日本に伝来以降は農耕行事と結びつき、五穀豊穣に感謝し、平安時代には里芋をお供えすることから別名「芋名月」とも呼ばれます。
そのため関西のお月見団子はこのお供えの里芋の形を模しているのだとか。

日本では月で餅つきをしていると言われるうさぎは、スロバキアでは春先のイースターのイメージが強いもの。
スロバキア人の主人からすると、うさぎと月、そして餅つきと馴染みのない行事が故に不思議そうに上新粉を捏ねる私を見ていました。
田舎暮らしを振り返ると
スロバキアでは人口200人ほどの小さな村で暮らしていました。
家の四方は平原と畑。
庭の裏手には小川が流れていましたし、少し散歩に出れば季節の草木が雑木林に生えていて、家に持ち帰り頻繁に室内に飾っていました。花というより、雑草や木の実の枝とか。
何気なくしていた日々の暮らしの行い、何もないと思っていた田舎暮らし。今振り返ると「何もなかった」のではなかったんですよね。
豊かさへの探求心
ちなみに今の家の周辺にススキなど生えておらず、店先にも置いてないので車道脇に生えていた雑草を花瓶に挿しました。
(これでも一応雰囲気は出る、、、)
スロバキアから日本へと生活の拠点が変わっても、変わり映えしない日々の生活の繰り返しだと決めつけず、豊かさへの探求心は常に持ち続けたいと思ったのでした。